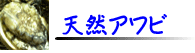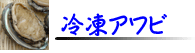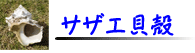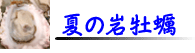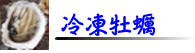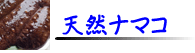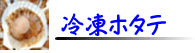牡蠣の生態・成分について
牡蠣の生態

名前の由来
諸説は色々ありますが「カキ」という名前は、岩に張付いている貝殻を掻き(カキ)落として採取することから付いたと言われています。
そして「牡蠣」という漢字は、漢語の「牡蠣(ぼれい)」を借用したもので、「牡」とはオスのことで、「蠣」とはゴツゴツした殻の形状を意味しています。
そうすると何故牡蠣がオスだけを指しているのかというと、大昔中国では「カキは塩水が凝結してできたものなのでオスしかいない。」と考えられたからだそうです。
まあ我々にはよく分からない発想ですよね。もちろん、牡蠣にはオスもメスもいます。
種類によって雌雄に分かれているもの、雌雄同体のもの、雌雄同体で時期によってオス、メスが入れ替わる牡蠣がいます。日本で冬に食べるマガキは「オス、メスが入れ替わる」種類の牡蠣になります。
オス、メスの入れ替わる生き物がいる事自体すごいことですが、牡蠣は生殖時期が終了すると一度中性になり、その後の栄養状態が良いとメスになり、悪いとオスになるそうです。
ですので、牡蠣はオスとメスが年によって変わります。
正に神秘ですね。
牡蠣の分類
○真牡蠣
日本名:マガキ(日本で冬に食べる養殖かき)
軟体動物-二枚貝綱-翼形目-イタボガキ科に属する二枚貝

○岩牡蠣
軟体動物-二枚貝綱-ウグイスガイ目-カイタボガキ科に属する二枚貝
別名:クツガキ、ナツガキ(夏牡蠣)

牡蠣の種類
世界には100種類以上の牡蠣がいると言われ、そのうち日本では、20種類程度生息しています。
一般的に有名なのは日本や韓国に代表され、冬に食べる真牡蠣です。
真牡蠣は、「広島型」「北海道型」「宮城型」「熊本型」に分類されています。
日本で生産されているマガキ以外の主な牡蠣には,イワガキ、スミノエガキ(有明海)、ケガキ(房総)、イタボガキ(淡路島、石川県)があります。
この他にも日本産ではありませんが、フランスガキやバ-ジニアガキ、オリンピアガキなどがあります。
牡蠣の特徴
牡蠣は古くから世界各地の沿岸地域で食べられ、薬品や化粧品、建材として利用されてきました。
その中で欧米では、生で食べられていた唯一の魚介類だそうです。
ローマ時代にはすでに初歩的な養殖が行われていたと言われ、牡蠣の別名である「海のミルク」という言葉も、その栄養豊富さを称えた欧米での牡蠣の呼び名になります。
また日本では江戸時代に、家の屋根に牡蠣の殻を敷き詰めて、火の粉が燃え移るのを防ぐように「牡蠣殻葺(かきからぶき)」屋根にしていたこともあったようです。
確かにバーベキューで殻ごと焼くと分かりますが、牡蠣の殻は燃えにくいですよね。
牡蠣は一見、合わせ目のない貝のように見えますが、アサリやハマグリと同じ二枚貝です。
冬に食べられるマガキや、夏の岩牡蠣などの大型種がよく知られていますが、食用にされない中型から小型の種も多く存在しています。
そのアサリやハマグリはどの貝でも全て同じような形をしていますが、牡蠣は貝柱が1つしかなく、生息する周囲の環境や、生息密度などによって殻が細長くなったり、丸くなったり、形が大きく変わり個性的です。
また、牡蠣はグリコーゲンを多く蓄える特質がありますので、他の貝と違って水が無い所でも1週間は生きることができます。
そして手にとって牡蠣をよく見ると、表面はゴツゴツしていますが殻の片側に丸みがあり、もう片側が平らになっています。この丸みのある方を左殻と言い、平たい方を右殻と言います。
牡蠣は受精後、約0.3mmの大きさになると、付着する場所を探します。
足を出して物の上を動き回ったり、気に入らないとその場所を離れたりします。
気に入った場所が見つかると、左殻を下にして、固着材(セメント質)を出して付着します。
そして一旦付着すると一生その場所を離れず動かなくなるので、牡蠣は筋肉が退化し内臓が殆どを占めています。
この「動かない」ということが、牡蠣の豊富な栄養素の秘密になります。
牡蠣の体内に溜め込まれる栄養素の中で、もっともよく知られているのが「亜鉛」で、他の二枚貝と比べ10倍以上の量を保有しています。
この亜鉛は新陳代謝を活発にし、美肌などの効果があります。
牡蠣の餌
牡蠣の餌は、植物性プランクトンなどで、昼も夜も休みなく1日中食べています。
餌を取り込むのには「エラ」を用い、大量の海水を吸い込み、中に浮かんでいるプランクトンをこしとります。
この時、牡蠣1個がろ過する海水の量は、1時間に約10リットル(ポリバケツ1杯分)にもなります。
ですので、海水中にいる時の牡蠣の胃の中は常に充満しています。
でも天然の牡蠣は干潮時には空気中にさらされ、餌を取れなくなりますので、効率を上げる為に考え出されたのが「養殖」です。
牡蠣が常に海水中にいれば、四六時中餌を取れるので成長が早くなります。牡蠣の場合は養殖でも味は落ちません。
牡蠣の養殖

日本で牡蠣の養殖地といえば、広島、三陸、伊勢、有明が特に有名です。
愛媛は知名度的には今一つですが、マガキ稚貝の多くは広島から仕入れていますので、広島型に近種の牡蠣に育ちます。
牡蠣養殖の歴史は古く、300年以上も前に広島湾で魚を囲い獲る「ひび」(木材や竹を海中に刺したもの)に牡蠣が付着したのをヒントにして、養殖が始まったという記録が残っています。
その後長い時を経て大正時代になって考案されたものが、いかだの下に連をつるす「垂下式養殖」です。この養殖方法によって牡蠣の生産量は飛躍的に増大しました。
牡蠣の垂下式養殖では、夏の初めの産卵期にホタテの貝殻を海中に吊るし、浮遊した牡蠣の幼生を貝殻に付着させ、後は餌が豊富な海域のいかだの下に吊るして放っておくだけというものになります。
牡蠣の養殖には、その他魚類の養殖の様に特別な餌を与える必要はなく、牡蠣が海の養分(プランクトン)をこしとって成長します。
生育する理屈は単純になりますので、自然の影響で大きく生育、生存率が左右されます。
高水温、台風、大雨、津波、赤潮等によるリスクがあります。
野生の牡蠣は餌が少ない磯などに付着するため、生育場所をよく吟味した養殖牡蠣の身の方が大きく、味も良いと言われています。
ですので、牡蠣にしても天然物だから良いというわけではないですね。
牡蠣を食べる!
牡蠣を食べる時期
○冬の牡蠣(マガキ)
秋~冬が旬で、「9月頃~4月頃まで」しか食べられません。
この時季には、牡蠣は体内に栄養を蓄えるのでグリコーゲンの量が最も多くなり、風味もよく、栄養価も高くなるので食べ頃です。
一方、「桜が散ったら牡蠣を食べるな」と言われています。
これは欧米でも言われていますが、英語で「R」のつかない月である「May、June、July、August」の5、6、7、8月は産卵期で、精巣と卵巣が非常に増大し、牡蠣の栄養価が落ち、中毒になりやすいので食用とするべきではない、ということです。
○夏の岩牡蠣
春から夏が旬です。
ですので、種類を選ばなければ年中美味しい牡蠣を食べられます。
牡蠣の生食用と加熱用の違い
牡蠣の場合、生食用の方が加熱用より鮮度が良いと思われがちですが、実は鮮度の問題ではなく「紫外線殺菌処理の有無」によります。
大腸菌やその他の細菌が、厚生省の定めた基準以下になるように、紫外線等で殺菌してあるものが「生食用」で、そうでないものが「加熱用」の表示になります。
「紫外線殺菌」とは、牡蠣を殻付きのまま滅菌海水の流水中に一昼夜ほど入れ、体内の雑菌等を吐き出させることになります。
しかし「紫外線殺菌法」では、牡蠣の身が小さくなる場合がありますので、業者の中には牡蠣本来の味にこだわってあえて殺菌せず、加熱用牡蠣として販売している所もあります。
和丸水産でもこだわりがありますので、紫外線殺菌はしません。
また、通常では「加熱用」ではカキフライ等にしますので、比較的大粒の牡蠣であるのが一般的です。
牡蠣の鮮度・品質の見分け方
○剥き身の牡蠣の場合(店頭で見かける、海水パックに入ったもの)
・パックに表示されている「賞味期限」「価格」「内容量」「産地」の確認。
・牡蠣の粒の大きさや色の確認。
身に丸みがありふくらんでいる牡蠣。また、縁の黒いひだが鮮明で、貝柱が透き通っているものを選んで下さい。
※古くなるとしぼみ、ひだ等どんどん崩れていきます。
○殻付き牡蠣の場合
・持って重みのあるもの、口が閉まっていてもの(生きています)
※牡蠣は死ぬと口が開きます。
食材としての牡蠣
牡蠣は食用としての歴史は非常に長く、世界中で食べられてきました。
一般的に肉や魚介の生食を嫌う欧米食文化圏でさえも、牡蠣は例外で古代ローマ時代から生で食べられてきました。(牡蠣は良くてもタコはなぜかダメなんですよね。)
最近日本で増えてきた「オイスターバー」は海外発祥(アメリカのニューヨーク)です。
海外では、ナポレオン、バルザック、ビスマルクなどが牡蠣の愛好家だったそうです。
一方日本では、貝塚で有名な様に縄文時代ごろから牡蠣が食べられ、ハマグリの次に多く食べられていたと考えられています。
室町時代頃には牡蠣の養殖が始まり、大坂では明治時代まで、広島から「牡蠣船」が土佐堀、堂島、道頓堀などにやってきて、船上で行商を行い、晩秋の風物詩となっていたそうです。
昔は輸送にかなりの時間がかかった為、産地以外で牡蠣を生で食べることはなく、もっぱら酢締めや加熱調理で食べられました。
日本人では、武田信玄や頼山陽などが牡蠣の愛好家だったそうです。
武田信玄はあわびも好んで食べていたらしいので、よほど海産物が好きだったんでしょうか。
生で牡蠣を食べる習慣があまりなかった日本人が変わったのは、欧米の食文化が流入した明治時代以降で、生食文化が欧米から輸入された珍しいケースです。
牡蠣以外にも同様のケースがなかったか探しましたが、ほとんどないようです。面白いですね。
牡蠣の食べ方
牡蠣の殻の表面は、剃刀の刃のように薄いものが重なっており、生食の際には軍手などの手袋を用いないと手のひらを怪我しますので注意して下さい。
牡蠣を食べる際には、身だけでなく殻にたまった汁も一緒に飲むと良いです。牡蠣のエキスがあふれ、多くの栄養素が含まれています。意外に美味しいですよ。もちろん、新鮮な牡蠣であることが前提です!
○生食
牡蠣の殻を合わせ目から、ナイフや牡蠣むきを差し込み、貝柱を切断してこじ開け、身をつまみ出して食べます。生ガキとも呼び、レモン汁、ポン酢等を使った酸味のある調味ダレを添えることで、より美味しさが増します。牡蠣独特の匂いも薄れます。(焼くと一番匂いが薄まります。)
○網焼き (焼き牡蠣)
牡蠣を殻のまま網の上で焼き、殻が開いたら食べます。一番手軽な食べ方です。
焼く際には、平らな面を下にしてまず焼き、殻が開く前に反対側にして下さい。
そうすると、貝の汁を残しつつうまく殻を開けられ、美味しく食べられます。
○カキフライ
生の牡蠣に小麦粉をまぶし、溶き卵をくぐらせてからパン粉をつけて、油で揚げる。
食べる際には、中の水分が高温になっていますのでやけどに注意して下さい。
○牡蠣の天ぷら
小麦粉を付けて揚げるものですが、牡蠣自体に水分が多く難しい料理の一つで、牡蠣の食べ方の中では主流ではありません。
○かきめし
牡蠣の煮汁でご飯を炊き、炊き上がった後に牡蠣を混ぜ数分ほど蒸らして作ります。
○カキ鍋
季節の具材とともに煮る鍋料理です。体が温まり、牡蠣を美味しく頂けます。ただし、牡蠣をあまり煮すぎると牡蠣が小さくなります。
○カキカレー
カレーライスの具に牡蠣を使ったものです。カレーの味が強まるので、牡蠣本来の味は薄れます。
○牡蠣の燻製
缶詰や真空パックで流通しています。作成に手間がかかるので、結構値が張ります。
牡蠣と食中毒の関係
牡蠣は古来より世界中で食べられてきましたが、「あたる」ものとしても知られています。
牡蠣の食中毒が注目されるのは、生で食べる(非加熱状態)ことが多いことに関係しています。
現在の日本で流通する生食用の牡蠣は、食中毒を回避するために生産・流通段階で対策がとられています。
生食用の牡蠣には加工基準が設けられており、食品衛生法により、
「大腸菌群最確数が一定以下の海域で採取されたもの」
「それ以外の海域で採取されたものであって、大腸菌群最確数が一定以下の海水、または塩分濃度3%の人工塩水を用い、かつ、当該海水若しくは人工塩水を随時換え、又は殺菌しながら浄化したもの」のどちらかであることが規定されています。
近年ではほとんどの業者が実施する殺菌方法として、三重県的矢の「佐藤養殖場」が1953年に確立した「紫外線殺菌された海水や人工海水などを、水槽内に循環させ、牡蠣を絶食状態にして数日間飼育する方法」があります。
この場合、牡蠣表面や内部に取り込まれた細菌の大部分を、体内から排出させほぼ無菌状態になることとは引き替えに、同様の処理がされていないものに比べ身が痩せてしまうことがあります。
そして食中毒症状を引き起こす原因として、「貝毒」「細菌(腸炎ビブリオ、大腸菌)」と「ウイルス(特にノロウイルス)」がよく知られています。
○貝毒
ある種のプランクトンの毒性が、それを摂取した貝に蓄えられた状態を指します。
カキの場合はアサリなどと違い、一般の人たちが海で採ることがほとんどないため、養殖業者等がきっちり検査をしていれば、ほとんどの場合、貝毒を防ぐことができます。
通常では都道府県の水産担当部局等により貝毒の検査が行われており、規制値を超えた場合は、直ちに出荷規制される仕組みになっています。
○腸炎ビブリオ
腸炎ビブリオは好塩菌と呼ばれ、塩分を好むので海中に一般的に存在しています。
一日の最低気温が15℃以上、海水温が20℃以上になると海水中で大量に増殖します。
ですので、冬場の牡蠣であればあまり気にする必要はありませんが、問題は水温の上がる頃に食べる「夏の牡蠣」ということになります。
とは言え、この菌は「貝毒」とは違い、海に生息するものであれば、何にでも付着している可能性があるので、牡蠣だけ気を付けたら良いというものではありません。
牡蠣に限らず、夏場の魚介類を生で食べる際は、腸炎ビブリオに気を付けて下さい。
予防のポイントは、
?魚介類は、調理前に流水(水道水)で良く洗って菌を洗い流すこと。
?魚介類に使った調理器具類は良く洗浄・消毒して二次汚染を防ぐこと。
?魚介類を調理したままのまな板で、野菜などを切らない(まな板を使い分ける)こと。
?夏季の魚介類の生食は十分注意し、わずかな時間でも冷蔵庫でできれば4℃以下に保存すること。(腸炎ビブリオは低温では増殖できません。また、低温で腸炎ビブリオの増殖は抑えられるものの、凍結しても短期間では死滅しません。)
?冷凍食品を解凍する際は専用の解凍庫や冷蔵庫内で行なうこと。
?加熱調理する場合は中心部まで充分に加熱すること(61℃、10分以上)。
○大腸菌
大腸菌の中でも病原大腸菌、 腸炎をおこす大腸菌を指します。
昔は食中毒が多かったようですが、現在ではほとんどの業者が、紫外線殺菌法により牡蠣の体内から大腸菌を排出させています。
○ノロウイルス
牡蠣の食中毒で最も一般的なのは、このノロウイルスによるものです。
細菌とは異なり、ウイルスの性質が悪いところは、牡蠣の中に存在していたとしても、その駆除が極めて難しいことや、ノロウイルスが人間を主な宿主として選定しているためです。
牡蠣の中では増殖せず、おとなしくしていて、それを食べた人間の中で増殖を始めます。
体力が弱っているとヒトの身体がウイルスに負けてしまい、発病することが多くなります。
ただし、ノロウイルスは「空気感染」することもあるため、牡蠣だけに注目しても意味がありません。
よく病院での院内感染等ありますよね。
ノロウイルスに当たると、高熱、下痢、悪寒などの病状があります。
どの原因も牡蠣が育つ海水に由来するもので、貝内部、特に消化器官(中腸腺など)に取り込まれ濃縮されます。
食中毒の予防としては、貝毒以外は「十分に加熱」することで回避でき、大量に食べることも控えたほうがよいとされています。
これは、A型肝炎ウイルスが経口感染する可能性が高くなるためです。
A型肝炎はその他の肝炎に比べて重症化・慢性化することは少なく、大抵は完治します。
さらに、15歳以上の日本人のほとんどはA型肝炎ウイルスに対する抗体(HA抗体)を持っているため、感染しても発病しないことが多いようです。
結論として、牡蠣を含むどの二枚貝も、「十分に加熱」することで、貝毒以外の食中毒の危険性を抑えられます。
牡蠣の成分・効能
成分・効能から見た、牡蠣を食されたい方
・貧血気味の方 ⇒ビタミンB12
・お腹の出てきた方 ⇒タウリン
・お酒が好きな方 ⇒タウリン
・視力の下がった方 ⇒カルシウム、マグネシウム
・精力増強を目指したい男性 ⇒亜鉛
牡蠣の成分・効能
牡蠣は「海のミルク」と呼ばれるほど栄養豊富で、たくさんの成分が入っており色々な効能があります。
[タウリン]
成人病に影響する「血中コレステロール値」や血圧の上昇を抑え、血栓予防や、網膜の発達や視力の回復にも効果があります。
また、アルコールの分解を助けたり、中性脂肪を減らす効果もあります。
[グリコーゲン]
牡蠣が含有する糖質の50%はグリコーゲンになります。
グリコーゲンは多糖類の一種で、体内のエネルギーが不足したときに等質に変化して血液中の糖度調節に使われます。
肝臓の働きを助けたり、疲労回復や体力をつける必要のある人に最適な栄養素です。
[良質タンパク質]
牡蠣には、私達の体を支えていくために欠かせない栄養素であるタンパク質がたっぷり含まれています。
牡蠣は食物からしか摂取できない8種類の必須アミノ酸をはじめ、全部で18種類のアミノ酸が含まれます。
[ミネラル・ビタミン]
ミネラルは骨や歯を丈夫にし、体の様々な働きを順調にする小児から成人まで不可欠な栄養素です。
鉄、ビタミンB1・ビタミンB2が多く、とくに鉄は100gあたり3.6mg含み、卵の2倍含みます。
さらに鉄の吸収を助ける銅が多く含まれ、牡蠣は貧血予防にかなり有効です。
またビタミンEが、血中の善玉コレステロールを増やすのに役立つため、動脈硬化や老化を防ぎます。
そして豊富に含まれている、カルシウムやマグネシウムは神経の興奮を鎮めますので、精神安定やストレス解消、高血圧予防、視力回復、などに有効です。
他には、精子をつくる亜鉛も豊富に含まれていますので、精力増強効果も期待できます。
この量は大きめのカキ一つで1日の亜鉛の必要量を満たすと言われます。
>夏の岩牡蠣の販売ページはこちら
>冬の御荘牡蠣の販売ページはこちら
  
|